家から締め出し、
私物を奪い、
親子の関係を断つ――。
これはれっきとした 「暴力」 であるにもかかわらず、日本では犯罪として扱われることもなく、被害者は泣き寝入りを強いられている。
そんな理不尽な現実の中で、たった一人で闘い続ける母親がいます。
今回ご紹介するのは、「追い出し」の被害に遭いながらも、子どもとの絆を取り戻そうと奮闘する2児の母・真美さん(仮名)の物語です。読むだけで胸が苦しくなる内容かもしれませんが、これは紛れもない「実話」です。
「離婚」の言葉が引き金に?
真美さんはそれまで10年間、フルタイムで働きながら家事と育児の中心を担ってきました。「もう少し家事を分担してほしい」「きちんと話し合いたい」―― 何度訴えても夫に真剣に取り合ってもらえず、ついに「離婚を考えたい」と口にしました。本来なら、ここから話し合いが始まるべきでしょう。
しかし、夫が取った行動は「話し合い」ではなく、彼女を家から排除するという暴挙でした。
ある日、仕事から帰宅すると、家の鍵が変えられていました。
中では子どもが泣き、母親に助けを求めています。インターホンを鳴らしても、ドアをノックしても、応じてもらえません。やがて夫が現れ、口論になりますが、「近所迷惑だから」と力づくで追い返されます。混乱しながらも冷静さを保とうとした真美さんは、少し間をおいて警察と児童相談所に助けを求めました。しかし、駆け付けた職員から返ってきたのは、耳を疑うような言葉でした。

「子どもに問題はないですね」
―― 母親が家から締め出されているにもかかわらず、です。
警察も児童相談所も、これを「問題なし」と判断したのでした。
家も、子も、奪われた
そして、その日を境に、真美さんが自宅に戻れることは二度とありませんでした。
彼女の私物はすべて家の中に残されたまま。

地域の役所に相談しても、「できることはありません」と取り合ってもらえず、住む場所すら失いました。それでも仕事を続けながら懸命に住居を探し、ようやく元の家から徒歩15分の場所に借家を見つけました。すぐそばに住んでいるはずの子どもたちに会うことすら許されない。これは本当に「家庭の問題」なのでしょうか?
母として、ただ子どもに会うために
行政の無力さに打ちのめされながらも、真美さんは母として動き続けました。
どうにかして、子どもたちと関わる方法を見つけなければ――。そこで彼女が考えたのが 「登校見守りボランティア」 でした。「これなら、子どもたちと毎日会えるかもしれない」
結果は、成功。
週に5日、ほんの短い時間ですが、登校する子どもたちと視線を交わすことができるようになりました。しかし、夫の監視があり、言葉を交わすことは許されません。それでも、母親としてできる限りの方法で、子どもに寄り添おうとしているのです。

本来なら、こんな涙ぐましい努力なしに、子どもに会えるのが「普通の親」なのではないでしょうか?それなのに、法的な救済は何もないのです。この問題は決して「一部の特殊な家庭」の話ではありません。今この瞬間も、日本のどこかで、同じように家を奪われ、子どもと引き離されている親がいます。もしあなたが同じ立場に立たされたら、どう感じるでしょうか?「法律が守ってくれる」と安心できるでしょうか?
家庭裁判所での戦い――果てしなく高いハードル
家も、子も奪われた真美さん。
次に頼らねばならないのは家庭裁判所でした。
しかし、日本ではいきなり訴訟を起こすことはできません。
「調停前置主義」といい、まず「調停」という話し合いの場を経る必要があります。
家事事件手続法第257条第1項 によれば、親権や養育費、離婚といった「人事に関する訴え」は、調停を経なければ訴訟に進めません。
一見すると穏やかで平和的な解決を目指す制度のように思えます。
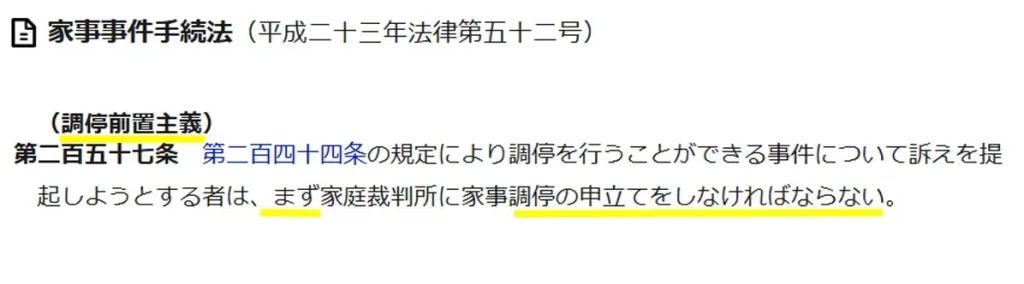
しかし、話し合いが長引くほど、会えない親子の間に溝が生まれるのも事実。
そしてこの制度の「建前」と「現実」のギャップに、真美さんも苦しめられることになります。
「話し合いをしましょう」と言われながら、そもそも子どもと会うことすら保障されない。その間に、子どもは母親との時間は奪われ、新しい環境を「当たり前」と思い込まされていく――。これが、本当に「子どものための制度」なのでしょうか。
「継続性の原則」は誰のため?
皆さんは 「継続性の原則」 という言葉をご存じでしょうか?
これは 「子どもの生活の安定を優先する」 という考え方ですが、解釈には2つの方向性があります。
① 「別居前までの環境に戻すこと」が、子どもにとって最も重要
② 「別居後の環境を維持すること」が、子どもの生活の安定につながる
国際的なルールである ハーグ条約(日本は2014年に批准)は、① の考え方を基本としています。
なぜなら、② を優先すると「実力行使による連れ去り」を正当化することになるからです。しかし、日本の裁判所は ② の考え方を主に採用しています。つまり、「先に子どもを確保した側が有利」 になる構造になっているのです。
真美さんのケースでも、裁判所は 「追い出し後の生活の継続」 を重視しました。
彼女が「主たる監護者」であったこと、また ネグレクト・DV・不倫が一切なかったことを認めながらもです。「子どものため」と言いながら、実際には「子を奪った親」の都合が優先されてはいないでしょうか?
未来への小さな希望――「共同親権制度」
そんな中、真美さんが わずかな希望 を抱いているのが、2024年5月に成立した改正民法です。この中には 「共同親権制度」 の導入が盛り込まれています。
もしこの制度が実現すれば、
◇ 親権獲得を目的とした子どもの誘拐が減る
◇ より平和的な離婚が可能になる
と期待されています。
しかしこの制度の施行は 2024年5月から「2年以内」。
つまり、最長で2026年5月まで待たなければならない のです。
待つには、あまりにも長すぎる時間ではないでしょうか?その間にも、子どもたちは成長し、親子の距離はさらに広がってしまいます。現行制度が 「機能不全」 を起こしているのであれば、一刻も早く改善する必要があります。
理不尽を変えるのは、一歩一歩の努力
真美さんは今も 子どもに会うため、見守りボランティアやPTA活動に積極的に参加しています。その行動力と忍耐強さには、ただただ頭が下がります。しかし、考えてみてください。「子どもに会うために、ここまで努力しなければならない」 ――この状況は、本当に正常なのでしょうか?
彼女は言います。「子どもが親を大切に思う気持ちを尊重してほしい。月に2回、夫の監視下でレストランで食事。こんな形でしか親子の時間を持てません。これが本当に『子どもの幸せ』ですか?」「ネグレクトもDVも不倫もないと裁判所は判断しているのに、それでも親子を引き裂くことを追認するなんて、司法としての責任を放棄していませんか?」
「追い出し」――これは決して単なる家庭内トラブルではありません。
国の運用が認めていないだけで、れっきとした暴力であり、人権侵害です。
親子の絆が 「法律の盲点」 によって引き裂かれる社会でいいのでしょうか。
答えは、明白です。真美さんの言葉を借りるなら「大人が責任を持って、子どもたちの気持ちを考えるべき」なのです。それこそが、より良い未来を築くために、大人が果たすべき義務なのですから。


コメント