妻との間に何が? 単身赴任の夫、自宅に入れず
2023年の秋、単身赴任をしていた吉田さん(仮名)(40代男性)が福岡の自宅に戻ると、信じられないような事態が待ち受けていました。
妻が内側から鍵をかけ、吉田さんが家に入ることを拒否したのです。玄関のドアをノックすると、彼女は警察を呼びました。駆け付けた警察官は「何もできない」と言い、むしろ彼女の言い分を優先するような対応だったといいます。「二人とも冷静になってから話し合ってください」と助言し、立ち去りました。その後、連絡を取ろうと何度も電話をかけましたが、ついに繋がることはありませんでした。
それから10日ほど経った頃、家の鍵が交換されていることに気づきました。現在も、自宅に戻ることは叶わないままです。
妻の「言い分」と夫の「決断」
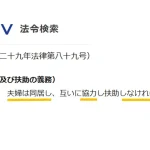
「確かにそれまで夫婦喧嘩はあったし、離婚の話もありました。しかし、あんなことができるなんて信じられません」と吉田さんは振り返ります。
専業主婦だった妻との合意で、自分名義の銀行口座を生活費として使っていました。給与の約9割をその口座に振り込み、妻がやりくりしていたのです。しかし家を追い出された後、弁護士に相談し、「給与の大半を妻に渡す義務はない」と判断。その口座を一時的に凍結しました。
当然、妻は激怒しました。しかし、吉田さんは当然の措置だと考えました。「民法には夫婦の同居義務、協力義務が明記されています。それを無視して追い出したのは妻のほうです」と。

直接連絡が取れないため、弁護士を通じて「なぜこんなひどいことをするのか」と尋ねました。しかし返ってきたのは、「あなたが私の時間を奪っている」「私の人生をめちゃくちゃにしたのはあなた」といった、予想を超える自己中心的な言葉ばかり。「もうやってられない」と思った吉田さんは、離婚調停を申し立てました。
その間、娘との交流は一切できず、家庭裁判所が標準とする月1回の面会すら叶いません。それでも妻は「離婚はしたくない」と言い張ります。離婚せずに別居した場合、「養育費」よりも高額な「婚姻費用」を支払わなければならないとされています。吉田さんは「こんなひどい仕打ちをしておいて、金だけは渡せということなのか」と、さらに強い不信感を抱きました。
自殺未遂を経て

2024年初め頃、吉田さんは極限まで追い詰められていました。「身代金目的の誘拐に国が加担している。救いはどこにもない」。そんな思いにとらわれていたのです。理不尽さに耐え続け、出口の見えない争いの中、「自分よりも大切な娘の成長を見守れないなら、生きる意味がない。もう終わらせよう」と絶望。心療内科で処方されていた抗うつ薬を約1か月分まとめて服用し、自殺を図りました。
…しかし、約24時間後に意識を取り戻し、一命をとりとめたことに気づきます。
「自分だけじゃない」── SNSの声が変えた、絶望からの再起
無気力な日々を送る中、ふとX(旧Twitter)を開くと、「連れ去り」「追い出し」「実子誘拐」という文字が目に飛び込んできました。言葉にできなかった自身の現状を的確に言い表す言葉の数々でした。そこには、自分と同じ境遇の人々の切実な声があふれていたのです。「こんなにたくさん、同じ思いを抱えている人がいるんだ…」。
当事者の声。当事者団体の声。支援者の声。親子関係を断たれても前を向く人々がいる。被害者に寄り添う人々がいる。自死を選んだ人を悼む声もある。それらは確実に吉田さんの心を揺さぶりました。「苦しんでいるのは自分だけではない」と。
「弁護士に任せるだけではだめだ」「自分で動かなければ、何も変わらない」。そうした投稿を目にするたび、吉田さんの意識は変わっていきました。
知識と行動で状況打開へ ── 当事者の声が力に
まずは当事者の話などを参考に、民法や家事事件に関する知識を収集し、自分のケースでどのように対応すべきかを考えました。国会で共同親権の議論が進む中、多方面の専門家、当事者、関係者の意見を聞いたり、官報など関連資料を読み込んだりもしました。中でも、当事者の生の声が彼に大きな影響を与えたといいます。
その過程で、裁判所では調停委員や弁護士の「夫婦間の事情」に対する理解や配慮の不足に驚かされることもありました。それでも吉田さんは、彼らを巻き込みつつ、自らも歩み寄る姿勢を見せました。その結果、妻の態度も徐々に軟化していきました。
娘との再会 ── 片親疎外の影、それでも縮まる距離
2024年の夏、ついに娘との再会が叶います。8か月もの間、何度願っても叶わなかった時が訪れたのです。その時の喜びは言葉では表せないほどだったと言います。

その日、5歳の娘は少し緊張した様子でした。手を伸ばすと、そっと握り返してくれましたが、以前のように無邪気に笑うことはありません。親と引き離された子どもに見られる「片親疎外(かたおやそがい)」の状態になっていました。小さな手を握ったまま、公園を歩きます。以前のように「高い高い」をせがむこともなく、どこか遠慮がちに隣を歩く娘。わがまま放題だった娘が、まるで別人のように大人しくなっていました。
月に1、2回の面会を重ねるうちに、少しずつ距離が縮まっていくのが分かりました。「幼稚園であやとりしたよ」「折り紙したよ」「友達がね…」そこまで話せるようになるには、数か月かかりました。
それでも時折、「○○ちゃんはお父さんとお母さんが一緒に来るんだって」などと、たどたどしい言葉で、それとなく不満を伝えてきます。その度に吉田さんは心が痛むといいます。しかし、会うことができなければ、娘は不満を漏らすことさえできません。その状況よりはずっとましだと、吉田さんは確信しています。
片親疎外とは:
同居親が不合理な理由により別居親を拒絶し、子供から遠ざけようとして別居親を誹謗中傷し、子どもを親嫌いとさせるものであり、学術上「片親疎外」と名付けられている。
出典:日米親権法の比較研究 / 山口亮子著
「当たり前」を取り戻した父の喜び

かつては叶わなかったことが、少しずつ現実のものとなっていきます。運動会で走る姿を応援し、発表会で緊張しながらも頑張る娘の姿を見守りました。人目をはばかり、陰で何度も涙をぬぐいました。ほんの数か月前まで、娘の成長を知ることすら許されなかったのに、今は隣で見守ることができます。
彼は親として、「両親が離れているのは、あなたのせいじゃないよ」と何度も伝えています。娘が無邪気に甘えてくることはまだ多くありませんが、「パパ、またね!」と帰り際、笑顔で手を振ってくれたことが、どれほど吉田さんの心を救ったことでしょう。
共同親権への一歩 ──「父の役割」と変わる未来
2025年初め、調停がまとまりました。離婚はまだ成立していませんが、娘との交流は月2回となり、幼稚園の行事にも参加できるようになりました。調停調書には「離婚する場合は共同親権を前向きに検討する」と明記されました。裁判官が「このような決定は異例だ」と述べると、吉田さんは「これから増えていくんじゃないですか」と皮肉交じりに言いました。これは、吉田さんが弁護士や調停委員に改正民法について何度も説明し、「共同養育」の重要性を粘り強く訴え続けた結果でした。当初は「父親の役割」など考慮されることすらありませんでしたが、少しずつ共同親権の意識が浸透し始めています。
それでも、まだ課題は山積しています。家庭裁判所の運用、弁護士の旧態依然とした価値観、行政の対応——どれも容易には変わりません。
しかし、変化の兆しは確かにあります。これからも吉田さんは、娘が「パパ、またね」と笑顔で言える未来のために、前を向いて歩み続けることでしょう。



コメント